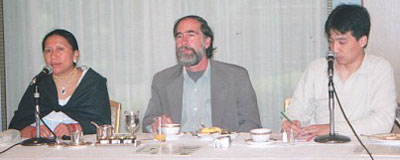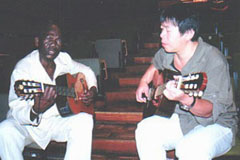| �i�}�P���m��y���Ƃ� | |
| �i�}�P���m��y���Ƃ� | |
| ����܂ł̎x���� | |
| ����ɂȂ�ɂ́H | |
| �i�}�P���m�͑ӂ��ҁH | |
| ���܂��܂ȓ��� | |
| �C�x���g����@�m�d�v�I | |
| ROR-JAPAN | |
| �n��ʉ݁u�i�}�P�v | |
| �X���[�J�t�F�錾 | |
| zoony(�Y�[�j�[)�^�� | |
| �W���p���E�A�Y�E�i���o�[�X | |
| 100���l�̃L�����h���i�C�g | |
| ����܂ł̊������� | |
| �ߋ��̃C�x���g�ꗗ | |
| 2001�N�̃C�x���g |
�t�B�G�X�^�E�G�N�A�h�� |
||
|
||
�t�B�G�X�^�E�G�N�A�h�����I���� �@�t�B�G�X�^�E�G�N�A�h�����I���܂����B��N�O�Ƀt�B�G�X�^���Ăт������i�}�P���m��y���̐��b�l�̂ЂƂ�Ƃ��āA���̎O�T�Ԃ��ӂ肩�����Ċ��z���q�ׂĂ݂����Ǝv���܂��B���̑O�ɁA���s�ψ��̂ЂƂ�Ƃ��āA���̏W�����Ƃ��ɂ��肠�������s�ψ���A�Q�����c�́A�{�����e�B�A�E�X�^�b�t�̒��Ԃ����A�X�|���T�[�A�����Ċe�C�x���g�ɎQ���������X�A��t�╨�̂ɋ��͂��Ă������������X�ɁA�ނ�Ŋ��ӂ��܂��B���蕶��������悤�ł����A�����̕��X�̋��͂���������A�t�B�G�X�^�����肦���̂ł��B���肪�Ƃ��������܂����B �@�t�B�G�X�^�̊J�Â��T�����X���P�P���ɕč��œ��������e�����N���A�P�O���W���ɂ͕ĉp�R�ɂ��A�t�K�j�X�^�����J�n���ꂽ�B�P�O���W���̓����͒�����J�A���̉J�̒��A�t�B�G�X�^�̃��C���C�x���g���s��ꂽ�B�܂����[�X�E�}���[�i�E���F�K�i�ȉ��h�̗��j�̃��[�h�ŁA�u�ЂƂ̎�A�ЂƂ̂�����A�ЂƂ̎v���E�E�E�v�Ƃ����L�`���A��ɂ��F��B�ڂ���i�}�P���m��y�����b�l�O�l���̊J�n�ւ̍R�c�̈ӎv�����߂Đ����\�����B�i���j����ɑ����ăA���j���E���C�g�ƃJ�����X�E�\���[�W���̃��[�h�Łu�C�}�W���v�������B���̓��̒��A�i�}�N�����b�l�̒����A�\���[�W���A�t�B�G�X�^���s�ψ����̋g���́A���̉̂��̂����Ƃ����߂Ă����Ƃ����B�t�B�G�X�^��O�ɒ����͂��������Ă����B�u��N�A�G�N�A�h���̃C���^�O�ŁA�J�����X�E�\���[�W���ƃA�j���Ǝ��͈ꏏ�ɁA�������̋��ʂ̖�����]�Ŗc��܂��邽�߂ɁA�C�}�W�����̂��܂����B���̊�]�̉́A�C�}�W�����A�����J���{�͋K�����A�G�����Ă��܂��B�������́A�t�B�G�X�^�E�G�N�A�h���ł��A�G�N�A�h���̐l�X�Ƌ��Ɋ�]�̉̂��̂������܂��傤�v �@�A���j���͂��̌�̔ޏ��̃c�A�[�ł��̉̂��̂��������B�����Ă����i�������̂��B�u���������푈�̂Ȃ����E��z������͂������Ƃ������l����������B�ł��������͑z������E�C�����Ƃ��B�z������n�������܂��̂�����v�B�����̌�A�ꕪ�Ԃ̖ٓ��B�Ŏn�܂�����������������I��鍠�A�Q���҂̓x���t�ƂƂ��ɉ̂��x���Ă����B����Ȍ�A�t�B�G�X�^�̊Ԓ��A�ڂ��͖����x���t�Ɨx�����B����܂ł����Ԃ�C�x���g�Ƃ���c�Ƃ����I�[�K�i�C�Y���Ă����ڂ������A����Ȃɗx�����C�x���g�͂Ȃ������B���C���C�x���g�̌�A�x����ꂽ�ڂ��炪�T�����Ńx���t�̃����[�i�̒a�������j���Ă��鎞�̂��ƁB���[�X�E�f���E�A���o���܂��ׂȂ���u�A�L�E�A�C�E���`���E�p�X�i�����ɂ͕��a�������ς��j�v�ƌ������B���̂��Ƃ��A�t�B�G�X�^�̊��Ԓ������Ƃڂ��̂�����̒��ɒʑt�ቹ�̂悤�ɋ����Ă����B�t�B�G�X�^�̎n�܂��T�ԑO�ɒ����͂��������Ă����B �@�u�t�B�G�X�^�E�G�N�A�h���ŗ�������l�X�́A�l�Ԃ����ł͂Ȃ��������A�A�����A���ׂĂ̖����ɂ��悤�Ƃ��Ă��܂��B�܂��A���������̐��ゾ���łȂ��A�������オ���a�ɍK���ɕ�炵�Ă�����悤�ȎЉ�����낤�Ƃ��Ă��܂��B���r�㍑���ł̎��R�j��^�̊J���́A�l�X�̐�����Ղł������j�i�n�����̈����������炵�j�����̓�ݏo�����ƂɂȂ����Ă��܂��B�@ �@�t�B�G�X�^�ŗ�������l�X�́A���R�̑f���炵���A�d�v�����悭�m���Ă���A���R�j��^�̊J���ɂ��ڐ�̗��v�ł͂Ȃ��A�q�ǂ������▢�����オ���a�ɁA�K���ɕ�炵�����Ă�����Љ�����낤�Ɗ������Ă��܂��B�e����푈�ȂǁA�\�͂��O�ʂɌ���Ă������̎����Ɉ��ƕ��a�Ɩ����ɂ���l�X���W���A�t�B�G�X�^�E�G�N�A�h�����J�Â��邱�Ƃ̈Ӗ����A���炽�߂čl���A���̈Ӌ`�������Ă���Ƃ���ł��v�i�i�}�N��ML���j �@�t�B�G�X�^�E�G�N�A�h���̓A�t�K�j�X�^���ւ̋�P�A�č��ł̒Y���ۃe�����������ŌJ��L����ꂽ�B�}�X�R�~�ɂ��Ă݂�A����ȑ�ςȎ��Ɂu�G�N�A�h���ǂ�����Ȃ��v�u�t�B�G�X�^�i���Ղ�j�ǂ�����Ȃ��v�Ƃ������Ƃ������낤�B���s�ψ���̗͕s���������āA���ɁA�t�B�G�X�^�����W���[�ȃ��f�B�A�Ɏ��グ���邱�Ƃ͂Ȃ������B���ꂾ���ɍ����I�ɂ��Ԏ��������Đh�������B�����A�}�X�R�~�ɏ��Ȃ��������A���O�̃l�b�g���[�N��}�C�i�[�ȃ��f�B�A�̒��ŁA�X���[���ŃX���[�ɍL�������t�B�G�X�^�̗ւɂ͓��ʂȈӖ����t����������Ƃ��A�ڂ��ɂ͎v����B�܂肻���ł́A�R�~���j�P�[�V�����̎�i����@���̂��̂����b�Z�[�W�Ȃ̂������B �@�u�b�V���哝�̂��u�e�������e�����v�A������u���`�������v�ȂǂƂ����q�����܂��ɂ��Ȃ�Ȃ���ґ���𔗂�A�u���_�v�Ȃ���̂�����ɑ傫��������Ă����悤�Ɍ����������Ȍ䎞���ɂ����āA�G�N�A�h������̃Q�X�g�����͉��߂Ăڂ������ɕ��a�Ƃ������Ƃ����̍�������l���������Ă��ꂽ�B�����Ă��̂��Ƃ̎��͂ɂ���l�X�Ȃ��Ƃ����B�����A�o�ϐ����A�R���I�D�ʁA�O���[�o���Y���A�G�l���M�[����B �@�ڂ������͂��̊Ԃɂ��A���S�Ŏ��R�ōK���Ȑ�����������Ƃ���A����͌o�ϑ卑�ŁA�R���卑�ŁA�G�l���M�[�卑�ɏZ�܂Ȃ�����s�\���A�Ǝv�����܂���Ă����̂ł͂Ȃ����B�܂�ł��̎����̍����A�o�ςƌR���ƃG�l���M�[�ɂ����ėD�ʂɂ����Ƃɂ���ăO���[�o���X���̉ߍ��ȋ����ɏ��������Ă����Ȃ�����A�����̖����͂Ȃ��Ƃł������悤�ɁB�����ł����O���[�o�����̔g�ɏ��x��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��������ϔO���A�ڂ������͂��̊Ԃɂ���������Ă����̂ł͂Ȃ����B�G�N�A�h������̃Q�X�g�����́A�F�A�u���S�Ŏ��R�ōK���Ȑ������v��ۏ��Ă����͂��̌o�ϗ͂��A�R���͂��Ȃ��u�n�����v�u�x�ꂽ�v�n�悩�����Ă����B��X�̂���܂ł̂��̂����Ō����A����́A�O���[�o�������鐢�E������c���ꂽ����ȁu��i�v�n��B �@�������A�ނ炪�t�B�G�X�^�E�G�N�A�h���Ŗ��炩�ɂ����̂́A�ނ炪�������łɊJ����O���[�o���Y���ɂ���āu��i���v��ǂ������郌�[�X���牺��Ă��܂��Ă���A����ɂ����u�����ЂƂ́v���B�W��������ݎn�߂Ă���Ƃ������ƁB��X���z���������Ƃ��Ȃ��悤�ȖL���Ȑ������l���ƕ������l�����A�J���Ȃ���̂ɂ���ĉ���A�ڐ�̗��v��o�ϐ����̂��߂ɔ��蕥�����肷��̂ł͂Ȃ��A�ނ��낻�������A�܂������Ɏ���邱�Ƃɂ���ĉ\�ɂȂ�u���S�Ŏ��R�ōK���Ȑ������v��I�ԂƂ������ƁB��X���}�����Q�X�g�����́A���E�e�n�Ɍ��������������V�������B�W�������A�G�N�A�h���ŕ`���A�������郊�[�_�[�����������B�����Ĕނ�͂��̐V�����R�~���j�e�B�ƒn��̃��f�����R�^�J�`�ɁA�o�C�[�A�ɁA�T���E�������\�ɁA�I�����h�ɑn��o������B �@���ꂪ�J�����X�E�\���[�W���̐V�������B�ނ͌������A�u����܂ł̖��������Ɖ��������A����ɂ���閲�����߂��Ă���v�ƁB���[�X�E�}���[�i�E���F�K�͂���܂ł̌o�ρieconomia�j�ɂ����V�����o�ρiecosimia�j�̃��B�W�������N�����B�@���̂悤�ɉ�X���������Ă����o�ς����R�╶���̎��Ȕے�ieconomia�Ƃ������ƂɊ܂܂�Ă���no�j�̏�ɐ��藧���Ă����̂ɑ��āA�V�����o�ς͍m���si(yes)�̏�ɐ��藧���낤�A�ƁB �@�u�O���[�o�������镶���v�Ƃ��嗬�̃��f�B�A�ɂ̂����u�����v�Ɋ��炳�ꂽ�҂̌܊����x���t��p�p�E�����R���͉�����Ă��ꂽ�B����܂Œ��ۓI�ȊT�O�ł����Ȃ������u���R�ƕ����̗Z���v���A�����ł͋�̓I�Őg�̓I�Ȃ��̂Ƃ��āA����悤�ȖL�����Ƃ��āA�ڂ����������|�����B �@���[�X�E�}���[�i�̎c���Ă��������b���Љ�āA�ڂ��̊��z���I��낤�B�u���鎞�A�A�}�]���̐X���R���Ă����B�傫���ċ������������͉��ɂƓ����Ă������B�������N���L���f�B�i���̒��j�ƌĂ��n�`�h�������́A�����Ɉ�H�������܂�ł́A���x�����x�����ł����Ă͔R���Ă���X�̏�ɗ��Ƃ����B��������đ傫���ċ������������̓N���L���f�B��n���ɂ��ď����B�u����Ȃ��Ƃ����ĐX�̉�������Ƃł��v���Ă���̂��v�B����ɓ����ăN���L���f�B�͌������B�u���́A���ɂł��邱�Ƃ�����Ă���́v�N���L���f�B�̓G�N�A�h���A�����ăG�N�A�h���œ����Ă��钇�Ԃ����B�ڂ��������N���L���f�B�ł��肽���B |
||
�t�B�G�X�^�E�G�N�A�h�����I���� �@10��6��������T�Ԃɂ킽��t�B�G�X�^�E�G�N�A�h�����A�傫�Ȑ��ʂāA�����ɏI�����܂����B�t�B�G�X�^�ɎQ�����ĉ��������F����A�{�����e�B�A�Ƃ��Ċւ���ĉ��������F����A���܂��܂Ȍ`�Ŏx�����ĉ��������F����A�����āA��N�O����t�B�G�X�^���������A�Ō�܂ł�萋���Ă��ꂽ���s�ψ��̊F����ɁA���ӂ������Ǝv���܂��B�ō��̃Q�X�g�ƃX�^�b�t�ƁA�ق�Ƃɑf���炵���t�B�G�X�^�ł����B �@������A�i�}�N���W�҂��S�̂ł܂Ƃ߂����ł���ł��傤���A����̓t�B�G�X�^���I�����u�G���v�𐢘b�l���炨�`�����܂��B �@�҂��S�̂̂��Ƃ������Ă����Ǝv���̂ŁA���́A�֓��̂��Ƌ�B�A���v�����ꏏ�ɗ��������[�X�}���[�i�ƃJ�����X�E�\���[�W���̂��Ƃ��������������Ă��������܂��B�i���͔����ԁA�Q�X�g�Ɠ��s���Ă��闯�璆�ɂ��܂����d���ɒǂ��Ă��܂��j �@���Ƃ��Ǝ����A�L�@�R�[�q�[�̐��Y�҂ł���J�����X����{�ɏ��҂������Ǝv�����̂́A���̂悤�ȗ��R���炾�����B�ނ炪�Z�ރC���^�O�n���̐X�сi���E���w�̐������l�����ւ�M�d�ȐX�тł���A�����̎���ł����邽�߂ɏd�v�ȐX�сj����邽�߂ɁA�X�тƋ����ł���L�@�R�[�q�[�͔|�^�����n�܂�A���̎��g�݂��x���L�߂邽�߂ɁA��N�O����R�[�q�[�̗A���i�t�F�A�g���[�h�j���n�߂��B���̃R�[�q�[�́A�_������w�엿���g�p���Ă��Ȃ��L�@�R�[�q�[�ł���ɂ�������炸�L�@�͔|�̔F�Ă��Ȃ��i�F�ؔ�p��葱�������_���ɂƂ��đ�ϓ���j���ƂƁA���݁A�\�����Ă��鍑�ۃR�[�q�[����̖�O�{�ōw�����Ă��邽�߂ɁA���{�����ł̔̔��ɋ�킵�Ă���A�J�����X�����{�ɏ��҂��邱�ƂŁA���Ƃ��̔�����L���Ă��������A�Ƃ̎v�������������炾�B �@�܂��A�C���^�O�̂���R�^�J�`�S�ł̑��̍������`�̑f���炵���𑽂��̓��{�l�ɒm���Ăق������A���̑��̍������`����u���ۑS�����̐錾�v�����܂ꂽ���Ƃ��m���Ăق��������B� �@�֓��ł̃t�H�[�����A�t�F�X�e�B�o���Ȃǂ��I������l�́A�����ŎO�J���A�F�{�A�����A�������A���v�����܂���ĕ��𗬉���J�����B�����ł͕��m���Ɗ����ɂ��đΒk���A�����ł͋��t�ł��萅���a���҂ł����鏏�����l����Ɂu�����a�W�v���ē����Ă��������A�ʐ^��f���Ȃǂ����Ȃ���ڂ�����������Ă����������B��l�Ƃ������ɂ͑傫�ȊS������A�G�N�A�h���ŕ��邽�߂ɖ{�������������߂Ă����B�r�f�I�͉p��ł��Ȃ��������߁A�����a�W�̎��s�ψ����ł���I���j������͂��ĉ��������B �@�C���^�O�ł͋��R�J���̖����������Ă���A�����̂邽�߂Ɏg�p����鐅�₪�����a�̌��������ł���̂ŁA�����̖{��r�f�I�͋��R�J���������~�߂邽�߂̋��͂ȕ���ɂȂ邾�낤�B� �@�������̏o���ł́A���ӂ��R���̈�茻���K�₷�邱�Ƃ���𗬂��n�܂����B �@�����A�G�R���B���b�W����肽���ƍl���Ă��鋳����_�����G�N�A�h���̎��g�݂���w�т����Ƃ̂��ƂŁA�_�Ƃ�_���̕�炵�ɖ��������b������������B�����Ŗʔ������Ƃ��킩�����B�J�����X�����R�_�@�ŗL���ȕ������M�̂��Ƃɂ₯�ɏڂ����̂ŁA�����u�V�q���D���H�v�ƕ����ƁA�����̓������Ԃ��Ă����B�����i�}�N���̐�y�Ƃ�������V�q��ނ́u�Q�O�N�Ԍ������Ă��āA���������ɘV�q�̖{��u���Ă���v�Ƃ����̂��B�Ȃ�قǁA���̐l�Ƃ͏��߂ďo�����������A���l�Ƃ͎v���Ȃ������͂����B �@10���W���̃t�B�G�X�^�E���[���C�x���g�̓��̑����A�ĉp�R�ɂ��A�t�K�j�X�^���̊J�n��m���Č��𗎂Ƃ��Ă����ނ́A���炭���Ď��Ɂu�����̃C�x���g�̍ŏ��ɁA�F�Łw�C�}�W���x���̂������v�ƌ������B���a�̐l�A�V�q�ƃW�����E���m���̓J�����X�̒��ł͂Ȃ����Ă���B� �@���E��Y�̉��v���ł́A��Ƃ̐���~�����S�ƂȂ��āA�u�[���G�~�b�V�������������鉮�v����c�v�Ɓu�L�@�}���S�[���Y�҃O���[�v�v�Ƃ̌𗬂�[�߂��B���E�ł����w�̉J�ʂ��ւ鐅�̓��ŁA����������㗬�ɂ̂ڂ鉮�`�D�ŊJ���ꂽ�𗬉�̓t�@���^�W�[�Ȑ��E�ݏo���Ă����B���v���́u�₭�v�Ƃ������t�̌ꌹ��q�˂���A�����Ȑ�������A�m���Ȃ��Ƃ͉��v���̐l�ɂ�������Ȃ��B���̎��A���[�X�}���[�i���u�L�`���A��Łw�₭�x�́w���x���Ӗ����Ă���v�Ƌ����Ă��ꂽ�B���̂����ꓯ�́A���̘b�ɕs�v�c�Ȋ������o���Ă����B �@�L�@�}���S�[���Y�҃O���[�v�́A�J�����X�����Q�����C���^�O�R�[�q�[�̎�����v���ō͔|���Ă݂邱�Ƃ����肵���B���̃R�[�q�[�����܂��������A�G�N�A�h���̃C���^�O�R�[�q�[�ƃu�����h���āA�G�R���B���b�W�E�u�����h�R�[�q�[�Ƃ��ĉ��v�����Y�Ƃ��Ĕ���o�����ƂɂȂ��Ă���B� �@��B�Ő����a�̎��ԂƉ��v���̐X�сi���E��Y�j�̑f���炵���̗��ʂ����āA�ނ�́A��������������Ă�������ɊԈႦ�͂Ȃ��Ƃ����v����[�߂��Ƃ����B�ނ炪�]��ł���u���W�v�Ƃ́A�o�ϕΏd�ł͂Ȃ��A�l�Ԃ̐����̎���l�Ԑ������߂�A�S�̖L���������߂�Ƃ������Ƃ��Ƃ����B �@�u���̍������`�v�̒��ł���u���O�c��v�͒N�ł����R�ɎQ���ł����c�ł���A�Z���^���̃��[�_�[�ł���J�����X�E�\���[�W�����S�̊��ی�ψ����ɑI�Ԃ��Ƃ����Ă��u�f���炵���Ȃ��v�Ǝv���Ă������A�����m��Ȃ������d��Ȃ��Ƃ�������킩�����B����́A���̉�c�ɂ͔N������Ȃ��A���w�������O�c��ɎQ�����A��l�Ɠ��������i���[���A�������Ȃǁj�����ׂĎ����Ă���Ƃ������Ƃ��B��l��600�l�Ŏq�ǂ���300�l���Q�����Ă���B���̂��Ƃ͂ƂĂ��d�v�Ȃ��ƂȂ̂ŁA����ڂ����������B� �@�̍Ō�ɁA�A���J�}���i���[�X�}���[�i�̃L�`���A���j�������Ă��ꂽ�L�`���A�̓`�������`���������B �@�u�A�}�]���̐X���R���Ă����B���ׂĂ̓��������́A��}���œ����Ă������B���ɑ傫�ȋ������������́A�^����ɓ����Ă������B�������ɂƂ��ďd�v�Ȓ��ł���N���L�����i���̒��j�Ƃ����n�`�h���̈��́A�������ɐ��H����H�Ƃ��ĔR���Ă���X�ɍs���A���̐X�ɐ��H�𗎂Ƃ��B�����āA�܂��߂��Ă��ẮA���H�������Ă����B��������āA�傫�ȓ��������́A�w����Ȃ��Ƃ����āA���������Ƃ��ł�����̂��x�ƃN���L������n���ɂ����B����ɑ��ăN���L�����́A�w���́A���ɂł��邱�Ƃ����Ă���́x�Ɠ������B�v� |
||
�F�l������ �@�҂��Ă��Ă��ꂽ�l�ɂ͂��҂����ˁA����Ƌߋ����ł��܂��I�A���j���ƃp�`���̓I�[�X�g�����A�Ɠ��{�̂R�����ɂ킽�钷�����������A�����̃v���W�F�N�g�Ɛ����s�����邽�߂ɃG�N�A�h���A�R�^�J�`�ɂ��ǂ�܂����B���ς�炸�ړ����̓��[���ł̘A���������ȏ�ɍ���ŁA�A�����r�₦�Ă��݂܂���ł����B �@���͏����ł����B�I�[�X�g�����A�ł͗F�l��Ƒ��₢�낢��ȂȂ���̂���l�����ƍĉ�A���ꂩ����{�̃t�B�G�X�^�E�G�N�A�h���ɎQ�����܂����B�M�щJ�я��Z���^�[�iRIC�j�݂̂�Ȃɍĉ�āA���N�̌v��ɂ��Ęb���������Ƃ��ł����͖̂{���ɂ悩�����B�W�����ƃ��X�̓f�B�[�v�G�R���W�[�̗��𑱂�����A�������l���ɂ��Ẳ�c�ɏo�Ȃ����肵�Ȃ���A�i�G�N�A�h�����܂ށj���E���̂�������̃v���W�F�N�g���x���������Ă��܂��B �@RIC�ɂ͂悭�ɂ����������p�[�}�J���`���[�̒뉀�������āA�d���ւ̑n�����ƃG�l���M�[�����ߒ����̂������Ă���܂��B�I�[�X�g�����A�ɂ͂����ЂƂ������뉀���o�C�����E�x�C��Seedsavers�ɂ���܂��B���̓~�V�F���ƃW���[�h�ɉ���āA�G�N�A�h���ɂ����Ƃ�������̃{�����e�B�A���������悤�ɂ���v��i�ł����2002�N�S������j���܂߁A�ނ��2002�N�̓�ĖK��v��ȂǁA���낢��Ȍv��ɂ��Ęb�������܂����B �@10���ɂ͎��̃p�[�g�i�[�A�}���Z���ƃp�`���A���̎O�l�œ��{�̃t�B�G�X�^�E�G�N�A�h���ɎQ�����鎖���ł��đ�ύK���ł����B����̓G�N�A�h���̐����I�A�����I���l���ɂ��āA���{�̐l�����ɂ����ƍL���m���Ă��炤���߂ɁA���x�ȃ}���`���f�B�A�����ɋ�g���ĊJ�Â��ꂽ��A�̃C�x���g�ł����B�R�^�J�`�A�C���^�O�A���ꂩ��C�ݐ��̃T���E�������c�I�A�o�C�A�E�f�E�J���P�X���\���ĂP�V���̃����o�[���G�N�A�h�����痈�����܂����B�������͓�͕�������k�͎R�`�܂ŁA�S���łQ�O�̃C�x���g�ɎQ�����Ȃ��炽������̏ꏊ�𗷂��܂����B �@�}�����o�Ǝ��̐V�Ȑ��Ȃ�g�ݍ��킹���V�����b�c���̔�����A��p�P�o�Ɉ���܂����i�b�c���~�����l�A�t�B�G�X�^�E�G�N�A�h���ɂ��Ă����ƒm�肽���l�͓��{�̃i�}�P���m��y���܂Łj�B �@�t�B�G�X�^�E�G�N�A�h���̂������ŁA�t�F�A�E�g���[�h��G�R�E�c�[���Y�������ĉ��y�Ƃ���������œ��{�ƃG�N�A�h�����J��[�߂Ă����V�����o���\���ɂ�������ŏo����Ƃ��ł��܂����B���ł��Ƃ�킯�d�v�Ȃ̂́u���W�v�Ƃ������t�̐V������`�⎝���\�Ȗ����ɂ��Ă̗��_�t���̎��݂��X�ɐV�����A�������邱�Ƃ��ł������Ƃł��B �@�Ԃ����̃p�`���Ƃ̃}���\�����E���f���s���I���āA11���ɃR�^�J�`�̖{���n�ɋA�ҁA�R�����̕s�ݒ��ɎR�ƂȂ���������O�ɂ��āA��x�Ɨ���ɂ͂��Ȃ��Ɛ������̂ł��i���Ȃ��Ƃ����̌�̈�T�Ԃ́I�j�I �@�ŋ߂̐��E�̏o�����̓G�N�A�h���Ƃ������ł̐����ɂ͒��ڂ̊W�͂Ȃ��悤�ł��|�����Ď��Ɋւ��ẮA�������Ƃ��ǂ��ɂ��悤�ƁA�ł��邾�������A�G�R���W�J���ŎЉ�I�Ɍ����Ȕ��W�̃��f�����������Ă�Ƃ������̎g�����ēx�m�F�����̂ł��I �@���C�`�F���i�I�[�X�g�����A�o�g�j�̎菕���ƉJ���̍ŏ��̈�~��̂������ŁA���͍���V������ň�t�ł��B�����ɁA�K��҂ɖ�ƁA�����ăC���X�s���[�V�������������Ă����悤�ɂȂ�ł��傤�B�Z���^�[�́A�Z���^�[�i�ƃJ�t�F�j���ɓn���Ċ��Ŏ�`���Ă���錣�g�I�ȃ{�����e�B�A��������܂ł́A�˗��̂������Ƃ������i�w����������ی�ψ���̃����o�[�Ȃǂɂ��j�J������ł��B���ꂩ�A��`���Ă����l��������A�m�点�Ă��������I �@�������́A�����������ی�̎��g�݁i���ɏq�ׂ��c�������ł��j�ɂ��ċٖ��ɋ��͂��Ȃ��犈�����Ă���R�^�J�`���ی�ψ���ɁA�������̃R���s���[�^�[�̂����̈��Ɠd�b����t���܂����B �@�C���^�O�̃G���E�~���O���|�C���^�O�̓����I�G�R���W�[�v���W�F�N�g�ɂ���ꂽ���O�ł����|�͏�肭�i��ł��܂��B�G�R���W�J���E�n�E�X�͂��܂�قڊ����i���Ƃ͐����ǂ����邾���ł��j�A�����Ċۂ������������ɂ��邷�Ă��ȃ\�[���[�E�V�����[���قڊ����ł��B �@500�{�̃R�[�q�[���̖w�ǂ��A�ɓx�Ɋ��������Ă������Đ����c��A�p�[�}�J���`���[�̔��͉Ƃ̎���ł���ɍL�����Ă��܂��B���̑傫�Ȏd���͉J���̊ԂɂȂ�ׂ������̌����̎�ނ̖Ɖʎ���A���邱�Ƃł��B���̈Ӗ��ł��A���R�Ƌ��ɐ�������ۓI�Ȍo�������Ă݂����A�܂��A�e�Ղɂ܂˂̂ł��鎝���\�Ȑ����������Ă݂����Ƃ����{�����e�B�A�劽�}�ł��B �@�o�C�A�E�f�E�J���P�X�̃Z���E�Z�R�ی��ɂW���ɍŏ��̃{�����e�B�A����������Ă��܂����B�����ł������ɂ��ւ�炸�A���d�����������Ă���A�܂��n���̃R�~���j�e�B�������āA�����犈�����s���܂����B �@�T���E�������c�I�E�p�[�}�J���`���[�Z���^�[�́A���܂��ɒ����̃{�����e�B�A�����Ȃ��A����������Ȃ��Ȃǂ̔Y�݂�����Ă��܂����A�ߋ��Q�N�̊Ԃɐ��������Ă����������A�����ւ̂悢��������ƂȂ�ł��傤�B���N�X���ɂ͓��{�����20���̑�w�����؍݂��A�����œ����o����l�X�Ȃ悢�`�Ńt�B�[�h�o�b�N�����Ă��܂��B �@���X�E�Z�h���X�ی��ł͂�������̃{�����e�B�A���p�[�}�J���`���[�̔��Ńo���o���d�������Ă��܂��B�����āACIBT�̃����o�[�����z�R�̌v�悳��Ă���n��ŃI���^�i�e�B���Ȕ��W���@�������߂邱�ƂɐϋɓI�Ɏ��g��ł��܂��B �@�����āA���ꂩ��́H�p�`���̐��b�i���X�����Ńn�C�n�C�Ɨ��Ƃ��Ƃ��Ă���j�A���̈����閺�������Ă���M�d�Ȏ��Ԃɍ��i��ł��邷�ׂẴv���W�F�N�g���`�F�b�N���A�������̐V�����v���W�F�N�g��i�߂邱�ƁI�V�����v���W�F�N�g�ɂ�2002�N�X���ɑ�K�͂ȑ�֓I�J���Ɋւ����c�ƍ��ۗL�@�R�[�q�[��c���J�Â��邱�ƁA�^���o�R�_��i�T���E�������c�I�̂��̎��n�ŁA�}���O���[�u��i�}�P���m�ی�悪����j�̃p�[�}�J���`���[�ƃG�R�E�c�[���Y���̎��g�݂��R�[�f�B�l�[�g���邱�ƁA�R�^�J�`�ł̎�q��s�̃v���W�F�N�g���g�債�A�������邱�ƂȂǂ�����܂��B �@�������͓��ɃR�^�J�`�ƊC�ݐ��̃o�C�A�i���̂ǂ�����G�N�A�h���ł͐��Ԍn�ی�n��̐錾�����Ă��܂��j�ł̉�c�ւ̎x�������肢���Ă��܂��B���̃C�x���g�̓G�N�A�h���ɂƂ��đ�Ϗd�v�ȋ@��ł���A���łɓ��{���炽������̏o�Ȃ��v�悳��Ă��邵�A�n�����{��R�^�J�`���O����̋��͂����܂��Ă��܂��B �@�������Ȃ����A���̃C�x���g�Ɋւ��A�����l�b�g���[�N��������A�������������Ă����\���̂���Ƃ����m���Ă�����A���̑��A�ǂ�ȕ��@�ł��x�����Ă����l�͂��点�Ă��������B���ꂩ�炠�Ȃ����ǂ̃v���W�F�N�g�ł�����ɏ�~�����ꍇ���A���������i���ꂩ�i�}�P���m�N���u��RIC�̃z�[���y�[�W�����Ă��������j�B�����Ă����K���i�����ĉ��x�ł��I�j�������A�C���X�s���[�V�����̕�ɂł���G�N�A�h���ɗ��Ă��������I�t�B�G�X�^�E�G�N�A�h�����x�����Ă��ꂽ�݂Ȃ���A���肪�Ƃ��B�t�B�G�X�^�����Ȃ������݂�ȂɃp���[��^���Ă��ꂽ���Ƃ�����Ă��܂��B �݂�Ȃ����C�ōK���ł���܂��悤�ɁB�A���Ƃ肠���܂��傤�B �����̂��߂ɁA�A���j�� |
||
����C���^�O�l���������{ �@���{�ւ̗��ɂ��ď����̂́A������Ɠ���B�قƂ�ǂ��ׂĂ̠�ʂɂ����āA�������̍��Ƃ͈���Č������B�������A���݂�ɉ�����l�X�Ȃ��Ƃ��w�B �@10��2������23���܂ł̗��ł������B�i�}�P���m��y���A���{�u���W���l�b�g���[�N�A�����ĉ������AAACRI����R�[�q�[���w�����Ă���P�C�{�[�A�������s�����̌l�I�ȓ����̂������ł���B��ނ�̎x������G�N�A�h���ł̃v���W�F�N�g�ւ̊S�����߂邽�߁A�����ăG�N�A�h���̕���������l���ɂ��Ă��悭�m���Ă��炤���߂ɔނ�̓t�B�G�X�^�E�G�N�A�h�����Â����B�����ЂƂ̖ړI�́A�C���^�O�̃R�[�q�[�̂��ƂƁA��X�̊�����邽�߂̐킢�̂��Ƃ����L���m�点�邱�Ƃł������B���̗��́A�o�ϊw�҃A�E�L�E�e�B�g�D�A�j���̍ȃ��X�E�}���i�E�f�E���E�x�K��t�A�o�C�A�E�f�E�J���P�X�̃}���Z���E���P���A�A�j���E���C�g����A�����ăT���������\�̉��y�ƃ_���X�̃O���[�v�A�x���t�ƈꏏ�ł������B �@���X�E�}���i��t�Ƃ킽���́A�u����̍u�t�����邱�Ƃɗ͂𒍂����B��薯��I�ȎЉ�Â���Ɏ��g��ł���킽�������̒n��̂��ƂƁA�����\�Ȕ��W���\�z���邽�߂̓w�͂�m���Ă��炢�A���̃v���Z�X�ɂ����ĕK�v�Ȏx�����邽�߂ł���B�����\�Ȕ��W�Ƃ́A���������邱�Ƃ̂Ȃ����@�œV�R�̎����𗘗p���A�ی삷�邱�ƁB����́A���̂��߂ł���A�����̐������邱�Ƃł���B�ݕ����g��Ȃ��I���^�i�e�B�u�ȏ��ƃV�X�e���A�n��ʉ݁iSintral�j�ɂ��Ă̓x�K��t���q�ׁA���ɋ������W�߂��B�F�l�ł���i�}�P���m��y���̃����o�[�́A���X���B�����߂����B18���Ԃ̓���10�̒n��ɂ����đS����14�̍u����𗬉���s�����B���ꂼ��̒n��́A1000���̐l��������s��������A�A�v�G�����������ȑ��܂ŁA�l�X�ł������B �@���̗��́A���ɂƂ��Ĕ��ɏd�v�ŁA�����I�ł������B���E�ň�ԁu���W�����v�Љ�̂����̂ЂƂ�̌����邱�Ƃ��ł����i���Ȃ��Ƃ��A�����I�L�����Ƃ����_�Łu���W�v���Ă���j�B�������A�킽���ɂƂ��čł��d�v�������̂́A�l�X�Ȑl�B�ƒm�荇���A�Θb�ł������Ƃł���B�������ƁA��ƉƁA��w���A��w�����A�����ƁA��w�A�_�Ə]���ҁB���{�̐l�B�̐e�Ɛl�̗ǂ��ɐG�ꂽ���Ƃ́A�킽���ɂƂ��đ傫�ȃC���p�N�g�ł������B����́A�ꕔ�ɂ͔��ɍ������烌�x���ɂ����̂ł��邱�Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ��ł��낤�B�i�Ⴆ�A�ǂݏ����̂ł��Ȃ��l�͈�l�����Ȃ��B�l����50���ȏオ�A��w������Ă���̂ł���B�j���̐��������̍����ɂ́A�ƂĂ����������B�킽���������K�ꂽ�V�ȏ�̎s�����ł́A�n�����l�X���������邱�Ƃ��Ȃ������̂ł���B� �@���������s�����ꏊ�����ʂ������킯�ł͂Ȃ��B�����ւ��s�������A�����̂悤�ɁA�L�g�Ɠ����l���������������ƌ�����s�s�ւ��s�����B�����ȑ��ւ��s�������A�Q���Ԃ͔_���̕Đ��Y�҂̂Ƃ���ł��߂������Ƃ��ł����B �@������30���G�N�A�h�������傫�������̂Ƃ���Ɉꉭ��疜�l���Z�݁A�G�N�A�h���Ɠ����悤�ɎR�̑������̍��ł́A�قڑS�Ă̎R�ŕی�[�u���Ƃ��Ă���B�����I�ɂ���قǖL���Ȃ��̍��ŁA70���̓y�n���X�ɕ���ꂽ�܂܂ŕۂ���Ă���Ƃ����̂��B������A�F�������������Ƃ̂ЂƂł���B���ʂȋ��Ȃ��ɓ��{�Ŗ�邱�Ƃ́A�܂��s�\���B�����������Ƃ�����Ō��Ă݂�ƁA���̕ی�́A����łق��̍��X�̐X�ɉe�����邱�Ƃɂ���Đ����������Ă����̂ł���B �@�ق��ɂ��������F�������������̂́A���ꂼ��̃C�x���g�̐������x�����Ⴂ�{�����e�B�A�B�̔��ȓ����Ԃ�ł���B���̎x�����Ȃ���A���̃C�x���g�͎����ł��Ȃ������ł��낤�B��ʋ@�ւɂ́A�F�J���������ӂ�����Ȃ������B�����A������̓d�ԁE�n���S���d�͂�����Ȃ��牽�S�����̐l�X���ڑ�����B�s�s���S���̓d�ԃT�[�r�X�́A�~�܂邱�ƂȂ������A�P�̓d�Ԃɏ��̂ɂT���Ƒ҂K�v�͂Ȃ������B���ʓI�ȃo�X�T�[�r�X������B���������炷���߂Ƀ^�N�V�[�̓K�\�����̂����ɃK�X���g���Ă���B�ǂ��ɂł����]�Ԃ𠌩�����邵�A���]�Ԃ̂��߂̃p�[�L���O�G���A�܂ł������B �@�S�̂Ƃ��āA�����₻�̑��̊��̂��߂̑[�u�ɂ���āA�傫�Ƞ�s�s�ł̓G�N�A�h���̓s�s�����������Ԃ������炳��Ă���B���Ȃ��Ƃ��킽���̌�������ł́A�s���A�n�������́A���{���A�䂪�����������Ɗ��ɋC��z���Ă���B ���W�̍����㏞�| �@�g��i���h�̒��œ��{���������W�r�㍑�̓V�R�����ɗ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B���̈ˑ��́A�H�Ɖ������啔���̍��ɂ����Ă�����ʓI�Ȃ��Ƃł���i�Ⴆ�A�A�����J���O���͖c��ȗʂ̐Ζ���A�����Ă��邽�߁A�G�N�A�h���₻�̑��̍��X�̊��j��������N�����Ă���B�j �����\�Y�꓾�ʌo�� �@���̒��ɂ́A�����ŋN�������l�I�A���w�I�Г�ɂ��Ă̓W�����������B���̓W���̐������������ɂ��Ă��������Ƃ������h�Ɍb�܂ꂽ�B�������́A���̔ߌ��̐ӔC�҂ł��鐭�{�Ɖ�Ђ����Ă̍ٔ������������邽�߁A�킢�̐擪�ɗ����Ă���w���҂̂ЂƂ蠂ł���B���̔ߌ��͔ނ̑����̐e�ނɂ��e�����y�ڂ����B �@1900�N�㏉���A���{�͂��ׂĂ��₵�čH�ƁA�o�ϖʂł́g���W�h��ǂ����߂Ă����B�H�ƓI���W�́A���{�̐����ƂɂƂ��Đ��Ȃ���̂ł���A�����̑啔����������ꂽ�_�b�ł������B�H�Ƃ́A���{�ɂ��S�ʓI�Ȏx�����Ă����B���C�̂���l�B�ɂ͠�H�Ɖ��ւ̐M�����_��A�\����Ȃ��v�����Ƃ��Ȃ��A�l�����ɂ��邱�Ƃ��Ȃ��ɉ����������B���̂悤�Ȑ��_��Ԃ��A���w���i�H�Ƃƒ��f�엿�𐅖��ɒ蒅�����A�����p�𐅋�ʼn��������邱�ƂɂȂ����B���̘p�́A���݂ł����������A�n��̐l�X�̐H�����ɂƂ��ďd�v�ȊC�Y���̌��ł������B���̂��߁A���X�ɐ����ɏZ�ގҒB�|�������̐l�X�A���A�L�A���܂ł��|�����łƂȂ��Ă������B�F���̘p������鋛�⋛��ނ�H�ׂĂ������߂ł���B �@�킽���ɂƂ��āA���{�؍݂ōł��S��h���Ԃ�ꂽ�̂́A�����ʼn߂��������Ԃł���A�������Ƃ̑Θb�ł������B�ނ͓W�����Ă���ʐ^��p���āA���₪�����ɂǂ̂悤�ȑŌ���^�����̂���������Ă��ꂽ�B�g�̏�Q�҂ƂȂ�A�l�Ԃ炵����D���A�H�ׂ邱�Ƃ��ł����A�������Ƃ��ł����A�m�b�x��ƂȂ�A���S�Ɏp��ς���ꂽ�A���l�ԂƂ�����l�X�B�������́A���ݐ����a�Ƃ��邱�̔j��I�ȕa�C�ɂ���āA�ǂꂾ���Ƒ����r�p������ꂽ����b���Ă��ꂽ�B���ׂẮA����ɂ����̂ł���A�l�Ԃ́u�~�v�Ƃ����a�C�ɂ����̂ł���B �@�܂��A��Q�҂Ƃ��̉Ƒ��ɕ邽�߂ɁA�����������N��������Ђւ̗v���Ɏ��g�E���Ȑl�X�̐킢�ɂ��Ă������̓W�����������B�ނ�́A�a�C�̌��������̉�Ђɂ���Ƃ̋^�����������B��������A���̕���̂����ЂƂ̔߂����͂��n�܂����̂ł���B�ǂꂾ�������Ƃ������ł͂Ȃ���Ђ�i�삵�Ă������A������r�f�I��|�[�g���ؖ����Ă����B��Ђ����{���A�����̌�������Ђ̔p����������ɂ���A�Ƃ������Ƃ��ؖ���������B���Ă����B����ɂ���ĉ����͈������A���t�ł͌����\���Ȃ��قǂ̂���Ȃ�ߌ����l�X�ɍ~�肩���邱�ƂƂȂ����B �@���N���̍���Ȑ킢�̌�ɁA�s���Љ�͂��̉�����H���~�߂邱�Ƃ��ł������̂́A�킢�͂܂������Ă���B�������Ƃ��̓����B�́A��Q��ґS���ւ̐����ȕ⏞�����߂Ă���A�܂��A�n�k�₻�̂ق��̎��R�ЊQ�ɂ���Ęp���×����N�������ꍇ�ɁA�C����ƂɎ��g�ޘJ���҂��Ō�����댯����J�����Ă���B���̒n��̕����̂��߂ɓ��{���{�́A���ɂ��̂悤�ȍH�ƃv���W�F�N�g�ɂ��������R�X�g�A�����Ơ�����z�ƃv���W�F�N�g�ɉ��S���h�����̂����𓊎����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���̃R�X�g�Ƃ́A�����Ă��n��̐l�X�̖��ƁA�����̐ŋ��ɂ���Ďx��������̂Ȃ̂��B �@���̋@��ɁA�����̊���Q�ɂ��ẮA�����čz�R�ɂ���ċ����ދ���������ꂽ�l�X�̂��Ƃ�Y��Ȃ����߂̉�c���J�������{�̌����҃O���[�v�̐l�B�ɏ��҂��ꂽ�B�����̉Ȋw�ҁA�����ƁA�s�������Ƃ��A�z�R�ɂ����ʂƎЉ�ʂւ̗l�X�ȉe���ɂ��ďq�ׂ��B� �@���ɂ́A�C���^�O�ɂ�������{��ƎO�H�ɂ��z�R�J���̎��s�ƁA�����̃v���W�F�N�g���~�߂邽�߂̉�X�̎��g�݂ɂ��Ęb���Ăق����A�Ƃ̂��Ƃł������B���̔��\�̌�A�����̌����҂炪�A�������̒n��ł̐킢���x������Ɛ\���o�Ă��ꂽ�B�����̃P�[�X�����Ђǂ��e���������N������邱�Ƃ������~�߂邽�߂ɁB �@�����ł̐����̊ԂŁA�H�Ɛ��Y�⏭���̌l�ɗ��v�������炷���߂ɁA�ǂꂾ�����R��Z���̐l��������Ԃ��D���Ă��������m�M���邱�Ƃ��ł����B���H�H��ɂ�鉘���͔��ɓŐ��������������߁A�������ӂ̐X�𐔃L�����[�g���ɓn���Ĕj���B�����Ɏ����Ă��A���C�̂Ȃ��R�����ڂɂ��A����𐭕{���ƂĂ�������p�������ďC�����悤�Ƃ��Ă���B�����̏Z���́A�j�ꂽ�ꏊ�̈ꕔ�����̂܂܂̎p�łƂ��Ă������B����́A������̂��߂̈��Ƃ��āA���R�J�������R��j���l�q���������̃��j�������g�̖����Ƃ��Ă̂��̂ł���B���܂�ɗL�Q�ł��������߁A�z�R������30�N�ȏオ�o�Ƃ��Ƃ��A�������̏���͉������ꂽ�܂܂ł���B �@�����ЂƂ�ۓI�������̂́A�����̎����Ǘ����Ă��镧���̑m�Ƃ̂�����Ƃ����o��ł������B��X�͎��@�̈ꕔ�Ƃ��Ă����֗���������B���̑m�͂����������ɏo�Ă��Ă���A�������R�ɂ���Ĉ����N�����ꂽ�����ƎЉ���Ɋւ���A�ނ̌�����b���Ă��ꂽ�B�w���O���[�v�����X�ɂ�����K��A�m�͂��̊w���B�Ɏ��R�A���ɐX���ɂ��邱�Ƃ̏d�v����A���l�Ԃ̐��_�ʂ̌��N�ɉʂ�����d�v�Ȗ����ɂ��Đ�������̂��Ƃ����B�ނ͑����ɂ����铺�R��Ђ̈����N�������傫�Ȕj����ƂĂ��J���Ă����B�Ō�ɁA�ʖ����Č��t�����킵����Ƃ��ł����B�ނ̈̋Ƃւ̊��ӂ̋C������`���A��X�̏Z�ޒn��Ŗڎw���Ă��邱�Ƃ������������b�������B�v���Ă��݂Ȃ������قǂ̔ނ̐e���A���ꂵ���v�����B�����āA�ނ̎��Ƒ����̊����ɂ��Ẵr�f�I���v���[���g���Ă��ꂽ�B�i�X�y�C����ł�����A�n��Ƌ���@�ւŎ��R�Ɏg����悤�ɂȂ邾�낤�B�j �@�����A�����K��ɉ����āA���X�E�}���i�E�f�E���E�x�K�v�l�ƒ������A�����ɂ����̗L�\�Ȓʖ�҂œ��n�u���W���l�̃N���E�W�I�Ƌ��ɁA���̃R�C���̗��ʂ����邱�Ƃ��ł����B���̑��Â���̐X�Ơ�̑�Ŕ��������R�ɂ��A���E��Y�ɂ��w�肳��Ă��鉮�v���ł���B �@���v���͍��̓�̕��ɂ���B���R��j���ɁA�����V�R�����𠊈�����Ȃ��甭�W����͉̂\�ł���A�Ƃ������Ƃ������Ă���Ă���B���v���́A�G�R�c�[���Y���Ǝ�H�|�i�A���Ƃɂ���Đ��藧���Ă���A�킽���ɂ́A���{�Ō������ł����̏Z������Ԃ悢��炵�����Ă���悤�Ɍ������B �@���̎R�����ȓ��́A��90�����V�R�̖��тɕ����Ă��āA�����̐����̒��ł����Ǝ��������������Ă���B���̐������͑����A�܂��悭�ی삳��Ă���B�������ŗV��ł���̂ɂ�������イ�o���킷�B�Ԃ�l��|����Ȃ����߁A�����^�]����Ƃ��ɂ͒��ӂ��K�v������B�������A��Ԗ��͓I�������̂́A����R�O�O�O�N�ȏ�̋���Ȑ��ł���B�����̎��̂��Ƃ֍s���̂ɁA�����قǂ悭����ꂳ��Ă��鏬��������B�X�̗l�X�ȑ��ʂɂ��Ă̊ŔƐ����������頂̂ł���B �@���v���ł́A���߂ē��{�̐l�X�̐e�ɐG��邱�Ƃ��ł����B����́A�ق��̖K��n�Ɠ����悤�ɁA������������Ă��ꂽ�F�l�B���A��X�����S�n�悭�߂�����悤�ɂƂł��邾���̂��Ƃ����Ă��ꂽ����ł���B�K�^�Ȃ��ƂɁA�Ď��A���쎁�Ƃ������A�ƂĂ����ʂȠ�l�B�Ɖ���Ƃ��ł����B�ނ�́A�����B�̓��̊�����邽�߂ɐ���Ă���B�s�����Ƃ��b�����B���n��錾�ɂƂĂ������������Ă����B�s���ɂȂ�����A�����̒n��Ƃ̊W���k�߂����ƌ����Ă����B �@���̓C���^�O�ɖ߂��Ă����B���{�łǂ�ȋ��P���̂��낤�B�������͂������牽���w�тƂ�A�ǂ����������Ƃ��ł��邾�낤�B�Ⴆ�A���Ɍ����ȕx�̕��z�A�킪���̍H�Ƃ����N���[���ȃe�N�m���W�[�A�����Ԃɂ�鉘�������悭�R���g���[�����邱�ƁA�s���ɂ���芈���Ȏ��R�ی슈���A�����ʓI�ł�艘���̏��Ȃ���ʋ@�ցB����A�킪���̐��{��͂����Ƌ���ɂ������₷���Ƃ��K�v�ł���Ƃ������ƂɋC�Â����B���ꂪ�A���{���卑�Ɛ��蓾���v���ł��邱�Ƃ͋^���]�n���Ȃ��B �@�����ЂƂd�v�ȋ��P�́A��X�̖]�ޔ��W�̂������ɂ��Ăł���B���{���o���������I�l�I�Г��A��X�����Њw�т������̂��B�����������藝���I�ɁA�A�C�f���e�B�e�B�[��ۂ��Ȃ���A�����Đl�ԂɂƂ��Ă̖L�����Ɗ��ی�Ƃ����a�ł��铹����߂�悤�ɁB |
||
�@�p�`���}�}�̂��ׂĂ̗ǂ��G�l���M�[���āA���Ȃ��B�����N�ł��邱�ƁA�����āA���A�т������E�����邽�߂ɗ��ł��邱�ƂƎv���܂��B������ł́A���̍������l�ԓI�ȍ��ɂ��邽�߂ɁA�ő�̓w�͂𑱂��Ă���Ƃ���ł��B �@�č��̖��ɂ��킽�������ւ̉e���͓������ɋ����Ȃ��Ă��܂��B�h�����͍s����ׂ��ł͂Ȃ������A�ł�����̂ł��B�������A�R�^�J�`�ł́A���ɗ������������@��m���Ă��܂��B�l���铪�����邵�A�������Ƃ̂ł���������B�����Ȃ鎞���A���X�Ɛ����Ă������Ƃ��ł���ł��傤�B �@���āA�����A�n���c��Ƃ̉�c�������܂����B���W�ƊǗ��ɂ��Ẳ�c�ŁA�ό��A���Y�A����ȂǁA���ׂĂ̈ψ����Q�����܂����B���ۉ�c�����̂��߁A�F���M�ӂ������Ďx���Ă����ł��傤�B �@�C�x���g�S�̂ɂ��Ă̒�Ă��������ɑ����Ă��炦�܂��H��������A����������̒�Ă����A���ۉ�c�ɕK�v�Ȃ��낢��Ȃ��̂�����Ă����܂��傤�B �@�F��������ׂĂ̈���������Ď��ꂽ���A�ƐS����v���Ă��܂��B������x�A���ׂĂ̐S�z��ɑ��āA������ׂ̂����Ǝv���܂��B���{�̐l�B�͂ƂĂ������I�ŁA�������ɃA�C�f���e�B�e�B�[�������Ă��܂��B�������S���ɗ^���Ă��ꂽ���ׂĂ̈���ɁA�������܂����B�����̉Ƃ̂悤�Ɋ������̂́A�L���[�o�l�Ɠ��{�l�Ƃ̎������Ȃ̂ł��A�{���ɁB �@�A�E�L�ƁA�R�^�J�`�̉Ƒ��S������A�������𑗂�܂��B���N�����K�p�N�i�n���̂ǂ��ɂ��Ă��A�������͏o����Ƃ��ł��܂��j��������̈�������߂āB �A���J�}�� |
||
10/8 �t�B�G�X�^�E���C���C�x���g�u�C�ƐX�̃t�F�X�e�B�o���v�i�ҐM��j �@�t�B�G�X�^�E�G�N�A�h���̂����Ȃ�����A�F����ɂ���B����X���ɂ̓A���j���A�}���Z���A�J�����X�A���[�X�E�}���[�i�A�������s�A�N���E�W�I�̈�s����B�ցB��Ɏc�����x���t���w�@��w���l�Z�ɂɂ��Ăт��āA�w�������Ɗy���������߂����܂����B��͕{���̃J�t�F�X���[�ŃT���T���}�����o�E�p�[�e�B�B�w���}���E�G�X�s�m�[�T�����y�y������Q�����Ă���A�������ɂ��肠����܂����B
�@�����āA�ߌォ��n�܂�C�x���g�̍ŏ��ɁA�݂�ȂŃW�����E���m���́u�C�}�W���v���̂����ƌ��߂��B
�@�F����A�t�B�G�X�^�E�G�N�A�h���̓A�t�K�j�X�^���ւ̋�P���������ŁA�܂��܂��\�͂̃G�X�J���[�g���鐢�E�̒��ő����Ă����܂��B�W���̃C�x���g�̃R���T�[�g�̍Ō�ɂ݂�Ȃŗx�������Ƃ̐S�n�悢���̒��ŁA���[�X�E�f���E�A���o���u���[�`���E�p�X�E�A�L�v�i�����͕��a�������ς��j�Ƌ����Ƃ�Y��܂��B
�@�ڂ���̃C�x���g�͂ǂ�������Ȃ��̂ł��B�傫�ȃ��f�B�A�ɂ̂�킯�ł��Ȃ��B�����ȍ��̏����ȑ��⒬���痈���Q�X�g�����́A�������ƂĂ��Ȃ��傫�ȃn�[�g�A��������Əd�����b�Z�[�W���A�ڂ������������łȂ�Ƃ��~�߂āA�������������Ǝ��͂ւƓ`���Ă�����������܂���B���ꂩ��̂ЂƂЂƂ̃C�x���g�̂ЂƂЂƂ̏o���厖�ɂ��܂��傤�ˁB |
||||||
�t�B�G�X�^�E�G�N�A�h������A���a�ւ̃��b�Z�[�W �@�܂��V���ȁu�푈�v���n�܂����B���ꂪ�Ō�̐푈�ɂȂ邩������Ȃ��B����͕s���ɖ��������E���琶�܂ꂽ�����B�v���Ύ������̋ߑ㕶���͒����ԁA��Ȃ��n�ɑ��āA��Z�����ɑ��āA�����Ă��݂����m�ɑ��Đ푈���������Ă����B����̂́A����Ȉ�A�̑����̐V������B �@�������ɂƂ��č��A���ɂ��܂��ĕK�v�Ȃ��ƁB����͎����̂�����̉��[���ɁA�����ς��̈��ƗE�C�����o�����ƁB�����Ă��̈��ƗE�C�������āA�V�������a�Ŏ����\�ȎЉ�̃��f��������o�����߂ɁA���Ȃ����̐��ɐh�����Ďc���ꂽ�����ƕ����̑��l���Ƃ�����Y����邽�߂ɁA�s�����邱�ƁB �@�ł���̂ǂ��ɂ���ȋ������A�E�C��T���o�����Ƃ��ł��邾�낤�H�@�����͂����Ƃ��Ȃ��̂�����̉��ɂ���͂��B�������͂悭�m���Ă���B�ЂƂA�\�͂����a���A���ݏo�����Ƃ͌����ĂȂ��Ƃ������ƁA���B�ӂ��A���͂ЂƂ�ł͂Ȃ��A�Ƃ������ƁB���̓{��A�߂��݁A�����ĕ��a��������C�����͎��ЂƂ�̂��̂ł͂Ȃ��Ƃ������ƁA���B�݂��A�������͈̑�ȃp�`���}�}�i��Ȃ��n�j�ƂƂ��ɂ���Ƃ������ƁB�p�`���}�}���������ЂƂ�ЂƂ���A���̖����̔��ƃG�l���M�[�������Ĉ��ł����Ƃ������ƁA���B Love, Peace and Life,
And now we need so desperately to find in our hearts enough compassion and enough commitment to actively create peace, and actively build new models of society and passionately defend the last vestiges of human- and bio-diversity. And how to find this strength? Be sure in what we know deep in our hearts; that violence can never bring peace; that we are not alone in our anger, sadness and love of peace; and that the power of Mother Earth, Pacha Mama gives boundless energy and beauty to nurture us as we continue to evolve... October 8, 2001, at Fiesta Ecuador, in Tokyo, Japan |
||
10/17�u�����l����o�ϐl�̉�21�v����F�@ �@���͂悤�������܂��B���Z�����Ƃ��남�W�܂肢���������肪�Ƃ��������܂��B�� �@�����G�N�A�h���O�ɁA����10�̑��q�}���e�B������u���{�ɍs���Ȃ炱��������Ă���v�Ƃ������Ƃ������܂����B����́u�����ւ̕s���v�ł��B����ꂪ�l�ԂƂ��Ăǂ̂悤�Ȉ��������Ă������Ƃ������Ƃ𑧎q�Ȃ�ɗ������A�������{�Ŕ��\���Ă��Ă���Ƃ����̂ł��B���q�͂܂��������̂ŁA�Ȃ����j�s���Ă���̂��A�Ȃ��l�ԊW�������Ȃ��Ă��Ă���̂��Ƃ������Ƃ́A�����͂�����Ƃ͂킩��Ȃ��Ǝv���܂��B�������A������l�́A���̗��R��������������͂��߂Ă��钆�ŁA�ǂ̂悤�ɂ��̖����������Ă����̂��Ƃ������Ƃ�����Ȃ���Ȃ�܂���B�݂Ȃ���������������ƂŏW�܂��Ă���̂��Ǝv���܂��B �@�����ŏ����A�G�N�A�h���ł̎��R�j��̌���ɂ��Ă��b�������Ǝv���܂��B�G�N�A�h���͔��ɐ����̑��l���ɕx���ł��B����́A���܂��܂ȋC���A�W���A���܂��܂Ȑ��Ԍn���G�N�A�h���ɐ����Ă��邩��ł��B�����̑��l�������ł͂Ȃ��A�����̑��l�����܂��L���ȂƂ���ł��B�G�N�A�h���͓��{��7���قǂ̖ʐςł����A����A���̎�ނ͓��{�̂R�{�ł��B����20�N�ȏ���Z��ł���C���^�O���������킪�����A�z�b�g�X�|�b�g����C���^�O�ɂ���܂��B��͔M�ъ����сA������͉_���тł��B���̏Z��ł���Ƃ����500ha����܂����A�����ɐ�������n�`�h���ƃ����̎�ނ��A�����J�ƃJ�i�_�����킹����ނ�葽���̂ł��B�R�^�J�`�͕W������300���`4,900���܂ł���A�G�N�A�h���̒��ł����ɐ����̑��l���ɕx�Ƃ���ł��B �@�܂��C���^�O���́u�������̒n��v�Ƃ������Ă��܂��B�������̐�Z�����A���l�A�~�X�e�B�[�\�A�A�t���E�G�p�g���A���i�A�t���J�n�G�N�A�h���l�j�Ƃ����l�������C���^�O�Ő������Ă��܂��B �@���̑������������̃C���^�O�������A��@�ɂ��炳��Ă��܂��B�_�Ƃ����ł͂Ȃ��A�l�ԂƎ��R�̃o�����X�������Ȃ�A���R�j�i��ł��܂��B�����j�ꂽ�̂́A���W�̈Ӗ����Ԉ���Ă�������ł��B�Ⴆ�A���N�O�Ɋ��j��v���W�F�N�g�Ƃ������ׂ��A�z�R�J��������܂����B����̓O���[�o���[�[�V�����������N���������Ƃ������Ă��܂��B�O���[�o���[�[�V�����̃��f���͂����_������܂����A���������z�R�J���̃v���W�F�N�g�͊��ɔ��Ɉ��������̂ł��B �@�O�����{��O����Ƃ����łȂ��A�����̐��{���O���[�o���[�[�V�����͂����Ǝv���đ��i���܂��B���邢�͐��E��s��IMF�Ȃǂ̈��͂ł��������v���W�F�N�g������܂��B���������́A���݃G�N�A�h���͐��E���ł��ŕn���A�ΊO���̑������X�̈�ɓ����Ă��邱�Ƃ���l���Ă��A���̃��f���͌��݂͂����g���Ȃ����f�����Ǝv���܂��B �@�C���^�O���ł͂����������f�����Ԉ���Ă���ƋC�Â��āA1995�N���玄����\�߂�c�̂����S�ɂȂ��āA�V�������f���������Ă������Ƃ���^�����n�܂�܂����B�����̉^���̖ړI�͎s���̂��߂̔��W�ł��B�ꕔ�̃G���[�g�A�ꕔ�̊�Ƃ̂��߂Ƀv���W�F�N�g�������߂�̂ł͂Ȃ��A�R�~���j�e�B�S�̂̎������߂邱�Ƃ��߂����Ă��܂��B�������Ȃ���l�Ԃ̖L������Njy����c�A�o�ϓI���W���߂����܂����A�S�̂Ƃ��Ă��������ɐi��ł������Ƃ��d�����Ċ������Ă��܂��B �@�������́A���╶��������Ă����V�������f���ɂ���āA������ɂ��ǂ������A��茒�N�I�ȎЉ���c����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ǂ������Ƃ́A10�˂̎q����������S�z����K�v�Ȃ��A�y���������ł���Љ�̂��Ƃł��B �@�������������Ɏ��g�ݎn�߂��̂́A�R�^�J�`�S�ɍz�R�J���̈��͂��������Ă�������ł��B�z�R�J���̊댯���������܂����B����ɑR����ɂ́A����ꂪ�R�~���j�e�B�̒��Ŏ���Ȃ��A�撣���Ă��������Ȃ��B�����DECOIN�iDefensa para la Conservacion Ecologica de Intag�j�Ƃ���NGO������A������\�ƂȂ��čz�R�J���̔��Ή^����W�J���܂����B�R�~���j�e�B�����ł͂Ȃ��A�S�m���⍑��NGO�A���{��NGO�̗͂���ē��������ʁA�Q�N����ɂ̓R�~���j�e�B�S�̂������̉��l���������܂����B �@DECOIN�ł͑��̍������`�����H���Ă��܂����A�z�R�J�����X�g�b�v���邾���ł͂Ȃ��A�o�ϔ��W�̑�ֈĂ��R�~���j�e�B�ɒ�Ă��Ȃ�������Ȃ��Ƃ����ӌ����o�܂����B�����Łu�X��Ȃ��A�z�R�J���͂��Ȃ��A���͉������Ȃ��v�Ƃ����e�[�}�ŁA�����B�ő�v����l���܂����B���̈���L�@�R�[�q�[�͔|�v���W�F�N�g�ł��B�������s����i?�E�B���h�t�@�[����\�j�Ƃ������̂����͂ŗL�@�͔|�R�[�q�[����{�ɗA�o���邱�Ƃ��ł��܂����B�������A�t�F�A�g���[�h�̌`�ł���Ă��܂��B�{���A�݂Ȃ���Ɉ���ł����������̂́A���������C���^�O���ō͔|�����R�[�q�[�ł��B �@�t�F�A�Ƃ����̂͏���҂������w�����邾���łȂ��A���Y�҂��K���ȉ��i�Ŕ̔����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B����ґS�̂��V�������f���������Ă������ŁA�t�F�A�g���[�h�Ƃ������g�݂�����Ɗ����Ă��܂��B���{�ɗA�o���Ă��邱�̗L�@�͔|�R�[�q�[�̏ꍇ�A���㍂�̂T�������ڂ����DECOIN��NGO�����Ɋ�t����܂��B���̂����Ŋ������^���𑱂��邱�Ƃ��ł���̂ł��B���z�I�Ɍ����Ƃ���قǑ傫���͂���܂��A��Ȃ����ł��B�������������͎������̊����̑��ɁA�ʂ̎����\�Ȕ��W�v���W�F�N�g�ɂ��g�����Ƃ��ł��܂��B�Ⴆ�A�z�R�J�����i�߂��悤�Ƃ��Ă����n��ŁA���̃R�~���j�e�B�ɏo�����āA�G�R�E�c�A�[�̑��i�ɋ��́E�x�����Ă��܂����B �@�G�R�E�c�A�[�𗧂��グ���R�~���j�e�B�́A�z�R�J�����\�肳��Ă���n��̒��ɂ���܂��B�v���W�F�N�g���{�i��������A�l�̃R�~���j�e�B���ړ]��]�V�Ȃ�����鋰�ꂪ����܂����B���̈���G�R�E�c�A�[�𐄐i���Ă������Ƃ́A�z�R�J���ւ̈�̑�֊����ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B���̒n��ł́A2,000ha�̌����т�ی삷�邱�Ƃ��ł��܂����B�܂��A�z�R�J���ɔ������܂��܂ȏd�����ɂ�鉘�����S�z����Ă�������A�G�R�E�c�[���Y���Ɏg���Ă��܂��B�G�R�E�c�A�[��ʂ��āA�R�~���j�e�B�̐l�������l�ԓI�ȂȂ���������Ă��܂����B���̑��ɂ��A�����O���[�v�������Ă��邳�܂��܂Ȗ��|�i�̎x����A���܂��܂ȃR�~���j�e�B�ւ̊�����̎w���Ɏ��g��ł��܂��B �@�V�������f���������Ă������Ŏ����d�v���Ǝv���Ă���̂́A���N�i2000�N�j����ŋ����ꂽ��Ⴞ�Ǝv���܂��B1997�N��DECOIN�́A���ꂩ��������Ȃ��甭�W���Ă������߂̂������̃|�C���g���u����v�ɒ�Ă��A���F����܂����B���ł́A�Ⴆ�H�Ƃ�Y�Ɗ����ɑ�������̃T�|�[�g�́A����j�Ȃ������ɑ��Ăł���Ƃ������Ƃ���������Ă��܂��B �@����ꂪ�]��ł���̂́A�H�Ƃ�Y�Ƃ��T�|�[�g���Ȃ��������ی삵�Ă������Ƃł��B�Ⴆ�ΐ����������Ȃ��H�Ƃ���юY�Ƃ�ڎw���Ă��܂��B���ɏd�����͂ƂĂ��댯���Ǝv���܂��B�܂��A���ɗD�������g�݂ɑ��āA�x����T�|�[�g�����邱�Ƃ�����ƍl���Ă��܂��B�����Ď������́A���╶����厖�ɂ����Ƃɂ����A���ł����Ăق����B�����\�ȎЉ������Ă������Ƃ�����Ƃƈꏏ�ɐV�������f��������Ă��������ł��B���̊����ɂ���ړI�̈�ɁA�u�V�������f���� �@���̓R�^�J�`�S�̊��R�~�e�̑�\�Ƃ��Ă��������Ă��܂����A�A�����J�A��A�����J�A����Ă̐V�������f��������Ă����Ƃ������Ƃ��A�݂Ȃ���̋��͂Ă���Ă������悤���肢�������̂ł��B���{�̎��ł��ǂ����̂ƃG�N�A�h���̎��ǂ����̂ƂŁA���ɐV�������f��������Ă����܂��傤�B���肪�Ƃ��������܂��B |
||
10/17�u�����l����o�ϐl�̉�21�v����F �@���͂悤�������܂��B����������Ŏ������̊������Љ�ł��邱�ƁA���ꂩ��̖��������b�ł���@��������������h�ł��B�������̓G�N�A�h���A�C���o�u���B�iImbabura�j�R�^�J�`�S�������Ă��܂����B�G�N�A�h���S�̂������ł����A�R�^�J �`�S�ɂ͂��܂��܂ȕ����A����������܂��B��Z���A���l�A�~�X�e�B�[�\�Ȃǂł��B�G�N�A�h���ɂ͐�Z���������ŋ�̖��������܂��B1996�N�Ɏ�������Z������� �����ƂƂ��ĕ\����ɗ����Ƃ��ł��܂����B���ꂪ�A�E�L�E�e�B�g�D�A�j���ł��B �@�R�^�J�`�S�́A�S�Ƃ��Đݗ����Ă���120�N�̗��j�������܂����A�A�E�L��120�N�����ď��߂đI�ꂽ��Z���o�g�̒m���ł��B����܂Œ����ԁA��Z���������A�C�f�A�������Ă��Ă�������g���Ă���Ȃ��A�܂��������@���l���Ă��Ă������I�Ɏז��������Ƃ������Ƃ����������߁A��Z���������ɎQ�����邵���Ȃ��Ƃ������ƂŃA�E�L�������ƂɂȂ�܂����B�������́A�������̂Ƃ��āA�����₻���ɏZ�ނ��܂��܂Ȑl�����̃A�C�f���e�B�e�B�����Ȃ��甭�W���Ă������Ƃɗ͂𒍂��ł��܂��B�����Ƃ����ɔC����킯�ɂ͂����Ȃ��̂ŁA�u����iAsamblea Cantonal�j�v�Ƃ����V�X�e���������čs���Ă��܂��B �@���̑���Ƃ́A�s�c��Ƃ͕ʂ̃V�X�e���ł��B�܂��e������I�ꂽ��\�ō\�������ό��A�q���A���Ȃǂ̃e�[�}�ɕ����ꂽ16�̃R�~�e�iComite =Committee�F�ψ���j������܂��B���̏�ɁA�e�R�~�e����̑�\�ō\�������R���Z�C���iconsejo�F������j������܂��B�����Ă���16�l�̗�������o�[����������W���A���̑���Ō��߂����Ƃ��s�c��ɒ�Ă���V�X�e���ɂȂ��Ă��܂��B���낢��ȃR�~�e�Ńf�B�X�J�b�V�����������e��y��ɁA�N�P��A����J����܂��B����͖����`�Ƃ��ďZ�������ڎQ���ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�P��ڂ�250�l�̎Q���A�U��ڂɂ�600�l�ȏ�̎Q���҂�����܂����B �@�����̍��̖����`�ł́A�Z�������[���Đ����Ƃ�I�сA�S�N��ɂ܂����[����܂ł͂Ƃ��ɉ��������ɉ߂����c�A�Ƃ������Ƃ��݂�ꂪ���ł��B�������������̖����`�ł́A�Z���͓��[������������̂܂܂ł͂Ȃ��A��ɎQ�����Ȃ��璬�̔��W�̂��߂̃v���W�F�N�g��i�߂Ă��܂��B�܂��A���̂悤�ȑ���ł������Ƃɂ���āA���ۉ��̖�����ĊO������̃��f����^�����Ă����̂ł͂Ȃ��A���̍������`�ł���Ă����Ƃ����V�������f���������Ă��Ă���Ǝv���܂��B �@�������͐l���ɂ��A�܂��A���肠�鎑�����Ɏg���Ă��܂��B���N���O�ɁA�G�N�A�h���ŐΖ���������܂����B���̖��c����K�v�Ȏ���������Ă���̂ł����A����Ɠ����ɂǂ�ǂ�n���̖�肪�������Ă��Ă��܂��B���̂悤�ȊW���������͖]��ł��܂���B �@�R�~���j�e�B���ɂ��邱�Ƃ́A�܂�l�Ԃ��ɂ��A�܂����������ւ̋�����d�v������Ƃ������Ƃł��B���������ƁA���N�O������A�̗L�@�R�[�q�[�͔|�v���W�F�N�g���n�߂܂����B�܂��A�����O���[�v��g�D���ăJ�u���i�T�C�U�����j�Ƃ����A������@�ۂ��Ƃ��Ė��|�i���������肵�Ă��܂��B�����͐l�Ԑ������߂�Ɠ����Ɋ��ی�ɂȂ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���āA���������v���W�F�N�g�������߂Ă��܂����B �@�܂��A���{�̕��X�Ƌ��ɂ���Ă�����ł��낤���Ƃ́A���[�J���o�ςW�������A���܂��܂ȕ��i�Ɋւ���t�F�A�g���[�h�ł͂Ȃ��ł��傤���B���Ȃ킿�A�L�@�͔|�R�[�q�[��G�R�c�[���Y���A���|�i�Ȃǂ������āA�����ȉ��i�ł��Ƃ�����邱�Ƃł��B���̍ہA�A�C�f���e�B�e�B�A�����A���ی�Ȃǂ̐V�������_�����ɗL���Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�t�F�A�g���[�h�ɂ���Ē����l���ł��邾���Ȃ�����A����ꂪ�]��ł��锭�W�ɋ߂Â��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̓����ȊW�Ƃ����̂́A����̉�Ȃǂ̏�Ŏ��������F����̂��Ƃ������ƒm�邱�Ƃɂ���Đ��܂�܂��B��������t�F�A�Ƃ������Ƃ������Ă����̂͑�Ȃ��Ƃł��B �@���ێЉ�Œʏ�g���Ă���f�Ճ��[���́A�ǂ��ɂł������悤�Ɏg�����Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B�����ғ��m�Ŗf�Ճ��[���������Ă�����Ƃ������Ƃ����͐M���Ă��܂����A�t�F�A�g���[�h�Ƃ����̂͑�ȃL�[���[�h�ƂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �@�܂��A�����𒆐S�Ɏ��g��ł���������̗�͒n��ʉ݂ł��B�������̃R�~���j�e�B�ł͍ŏ��A���X����������Ă��Ă��܂����B���ꂪ�n��ʉ݂ւƐi�������̂ł��B�H�Ƃ̈��S�����ɂ��Ȃ���܂����A���̂����ɃT�[�r�X���������邱�ƂɂȂ�A���݂ł͂������g�����Ƃ͕K�v�Ƃ���Ă��܂���B�������͂����̑���ɁA�u�N���i�����j�v�ƌĂ�鎆���^�C�v�̒n��ʉ݂��g���Ă��܂��B����ŕ��ƌ���������T�[�r�X������肵�Ă��܂��B �@�����̂Ȃ��l�����̒n��ʉ݂ɂ���ĐH�ׂĂ�����̂ŁA�������@���Ǝv���܂��B�������̂悤�ɏ����������̂ł��A�n��ʉ݂Ȃ玩���B�Ŕ��s���邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�n�悾���łȂ��������z���āA�Ⴆ�Γ��{�Ƃ�������������肪�ł��܂��B���{�ɐH�ו���A�o���āA���{�̋Z�p��A������Ƃ������Ƃ��\���낤�ƐM���Ă��܂��B���{�ƕ��X�����Ȃǂ��ł���Ǝv���܂��B�����͂��C������ł���Ǝv���܂��B�R�^�J�`�S�Ƃ��Ă͂��C������܂��B �@�����A�O���[�o���[�[�V�����̐��b��ɂ���Ă��܂����A���͂悢�Ƃ���������Ƃ��������Ǝv���܂��B�Ⴆ�A���W�r�㍑�Ɛ�i�����ꏏ�ɕn���̖��Ɏ��g��ł����A�t�F�A�g���[�h�Ȃǂɂ���ăt�F�A�Ȃ������ŋ������Ȃ��瓧���ȊW��ۂ��Ă������Ƃ́A�O���[�o���[�[�V�����łȂ�\���Ǝv���܂��B�܂��A���ی�̖ʂł����ɂ������@�ɂȂ�Ǝv���܂��B��قǂ��b���܂����A�����������g��ł�����ی�͓��{�Ƃ̂Ȃ��������Ǝv���Ă��܂��B�������A�O���[�o���[�[�V�����͎g�����ɂ���Ă͈������ʂɐi��ł��܂��Ǝv���܂��̂ŁA���ӂ��K�v�ł��傤�B �@�܂��A�R�^�J�`�ł͂܂��܂����E�������̂ŁA���̉��E��r�����銈�������Ă��܂��B�����̂��܂��܂Ȋ������F�߂��A��N�i2000�N�j10���ɂ́A���A�l�ԋ��Z�Z���^�[�u�n�r�^�b�g�v�ƃA���u���A�M�̃h�o�C�s���A�u2000�N�h�o�C���ۏ܁v�����������܂����B���̏܂͂Q�N���ƂɁA���ی��n���팸�A�����ȎЉ���Ȃǂɍv�����Ă��鎩���̂�NGO�A���f�B�A�Ȃ�10�c�̂ɑ�������̂ł��B����A�R�^�J�`�S�́A���̏Z���Q���^�Љ�V�X�e���Ɠ������̂��鎩����]������܂����B �@�܂�A���������]��ł��锭�W�Ƃ����̂́A�l�Ԑ������߂�A�l�Ԃ̐����̎��A�S�̖L���������߂�Ƃ������ƂȂ̂ł��B�������́A�o�ς����łȂ������̎������߂邱�Ƃ��l���āA���܂��܂Ȋ��������Ă��܂��B �@����A���{�ɐ��T�ԑ؍݂��Ĕ��ɗL�Ӌ`�Ȍ��w���ł��܂����B��B��K�ꐅ���a�̎��Ԃ����Ă��܂����B�܂��A���v���ł͐��E��Y�ɓo�^����Ă�����̂��炵�������Ă��܂����B���ɂ��Ă͗��ʂ����Ă����킯�ł����A����̓R�^�J�`�Ɏ����ċA��邢�����ɂȂ�܂����B �@�����āA���̓�̏�i�����邱�Ƃ��ł��āA�R�^�J�`�Ŏ�����������Ă��邱�Ƃ͐������̂��Ƃ����m�M��[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B���N�i2002�N�j�X���ɃR�^�J�`�Łu���E�B�[�N�v���J�Â��܂��B�܂��ڍׂ͌��܂��Ă��܂��A���{����Q����\�����Ă��������������Ⴂ�܂��B�݂Ȃ���̒�����������̕��ɎQ�����Ă��������A�R�^�J�`�S�ɐe���݂������A����̂��Ƃ𗝉���������W�ɂȂ��Ă�����Ǝv���܂��B�S���J���đ҂��Ă��܂��̂ŁA��낵�����肢�������܂��B���肪�Ƃ��������܂����B |
||
���O���[�v���u�x���t�v�̗R���Ɣނ�̂���ꏊ�w�i�F �x���t�F�ނ�̌��t�Łg��������h�Ƃ����Ӗ��B�O���[�v���u�x���t�v�́A�u�A�f�B�I�X�E�x���t�v�Ƃ����`���I�}�����o�y�� �ɗR������B�u�A�f�B�I�X�E�x���t�v�́A���̒n���ɓ`�����̖��b�B �G�X�������_�X�B�F�A�t���J�n�E�G�N�A�h���l�̏W������n�����G�N�A�h���̒��ł��ł��n�����A�}������Ă����ꏊ�B
�@ ���̍��A��ҒB�̓}�����o�ɂ��āu�ÏL�������v�Ƃ����C���[�W�������Ă��āA�S���S�������Ȃ������B�J�����X���r�I�A�A�i���f�B�A�v�Ȃ́A�����j�����Ɋւ��d�v�ȕ����Ƃ��Ẵ}�����o�̈Ӗ���������x��ҒB�ɗ������ė~�����Ɗ���Ă����B �@�����ŃR���q�I�ɂāA�u�c�悩��`����ꂽ�d�v�ȕ����v�Ƃ��Ẵ}�����o��������R�[�X�������Ƃɂ����B�����A�����������l�͂��܂�Ȃ��������A�F�B����F�B�ւƌ��`���ŕ]�����L�܂��Ă����B����ł��A�ŏ��ɂł����}�����o�O���[�v�̊����͂��܂��肭�s���Ȃ������B���r�I�����l�łȂ����Ƃɂ��N�����A�W�c�Ƃ��Ă̂܂Ƃ܂肪��肭���Ȃ������̂��B �@�ނ�̓R���q�I�ŋ����邱�Ƃ�f�O���A���̎��̒��ԂV�l�Ƌ��ɐV�����O���[�v�����������B1980�N�̂��Ƃł���B�Q�l�̃}�����o�Ђ��A�Q�l�̃N�k�[�m�A�Q�l�̃{���x�[���A�P�l�̗x���A68�ˁA80�A90�A�O���~�I�̂�������A�V����X�̂T�g�̒j���i���̒��ɂ̓J�����X�ƃA�i���f�B�A�̂��ǂ��Q�l���܂܂�Ă����j�B�Ⴂ���B���A�i���f�B�A��炢�W�܂�A���̏��̎q�B���܂��A�Ⴂ�j�̎q�B��A��ė���Ƃ����悤�Ƀ����o�[�͎���ɑ����Ă������i2001�N���݂�100�l���������W�c�j�B���ꂪ�}�����o�W�c�u�x���t�v�̎n�܂�ł���B �@�A�i���f�B�A��1950�N�A�G�X�������_�X�B�s�G�X�������_�X�s�Ő��܂ꂽ���l�̏����B���߂̓R�����r�A�@�g�D�}�i�T���������\�Ɠ����������j�ŗx��̐搶�����Ă����B�����̐l�ɕ���A���̒��O�܂Ŗ����ɑ��k�ɂ���l�������Ȃ������Ƃ����B�ޏ��̋���ɂ͏�ɁA���I���ʁA�Љ�I���ʁA�����I���ʂƂ����R�̗v�f����̂ƂȂ��Ă����B �@���݃T���������\�̒����ɂ���x���t�̏������ł���O�́A�Sm�~�Sm�̏����ȕ����ŋ����Ă����B�y��͕ǍۂɊāA�����������Ȃ���x�����B�₪�āA�����ƍL���Ƃ���ŋ����邽�߁A�~���K�i�����̂̂��߂̖����J���j�ɂ���ĐV�������������邱�Ƃɂ����B�V��j���A�����鐢�オ�y�j���ɏW�܂�A���݂Ɋւ�����B����Ȃ��Ƃ����Ă���ޒB���o�J�ɂ���l�X�������B �@�r���ōޖ��s�����A�w�����邽�߂̎������Ȃ������̂ŁA�R���ɓ����|���Ă͐�ɗ����i�������ꏏ�ɗ���Ȃ���^�сA�j�傫�ȏ��������Ă��B���������͒��̋��͂āA���邱�Ƃ��ł����B�Ǎނ͒|�B�|�т̎����傪�u��ŕ����Ηǂ��v�ƒ|��݂��Ă��ꂽ�B �@�������Ăł����w�Z�ł́A�̂����ƁA�y����Ђ����ƁA�x�邱�ƁA�y������邱�Ɓi�܂��y��̍������w�Ȃ��Ɖ��t�����Ă��炦�Ȃ��̂��x���t�̃X�^�C���j�A����ɉ����ē`��������������ꂽ�B �@�^�c������INFA�Ƃ������̋@�ւ��A�ŏ��͉������Ă���Ă����B���̉������Ƃ܂�������A���݂Ɏ���܂Ő��k���猎�ӂ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B ���@���@�� �� �ȉ���i�ꕔ�j�F �EBambuco�F�@��c����`����ꂽ�`���I�y�ȁB���l�ł����т��̂��B ���x���t�o���C�x���g�ꌾ�i�����j�F �E10/6�I�[�v�j���O�E�Z�����j�[�i�J�t�F�X���[�j �E10/7�t�B�G�X�^�E�G�N�A�h���E�C���E����i�|�p�̉Ɓj �E10/9�T���T�_���X�����i�J�t�F�X���[�j �E10/15�є\�R���T�[�g
�@�p�p�E�����R�����M�^�[��e���Ƃ͒m��܂���ł����B���߂āA���n�ł��̑t�@�Ɖ̂����Ƃ����ɑł��ꂽ�v���ł��B�����āA���X���A�y���Ŏ����M�^�[��������Ă���ƁA�p�p�����̏��ɃC�X�������ė��āA�ԋ߂ɍ���A�R�~���j�P�[�V�������n�܂�A���̂����AMystie ��N���T���^�������A�p�p�̋Ȃ̃Z�b�V�����Ɉڍs���Ă����܂����B���̂Ƃ��̃p�p�̃��b�Z�[�W���܂��`���܂��B �@���ꂼ��ٍ̈���ŃA�����W�ł���悤�p�V�[�W����`�������B���ꂱ���������𗬂ł���B �@�y���ł̃Z�b�V�������Ƀp�V�[�W���̑t�@�����ɓ`�����Ă���A�������A�e�X�g�E�p�X�������悤�ŁA���Y���E�M�^�[�̂��w�������������܂����B�i�Ȃ�Ƃ������h�I�j���Y���E�M�^�[������ƃp�p�����R�Ƀv���C�ł��܂��B�i���͂��̖ڌ��ҁj�����āA�o�b�N�E�R�[���X�B���̕Ґ����p�V�[�W���̃G�b�Z���X��`������ŏ��`�Ԃ̂悤�ł��B �@�p�p�E�����R���̃M�^�[�̒e�����͕M��ɐs�������������̂�����܂��B�M�^�[��I���A�E�����p���t���Ɏ����ւ��Ă̔ޓ��L�̑t�@�͒������̂ł��B�܂��ɁA����Ȃ炸�f����ł��B�ނ̃p�V�[�W���̃p�t�H�[�}���X�͊ԈႢ�Ȃ����{�ł���^�������̂ƒf�����܂��B���̉̂ƃM�^�[�t�@�ƃ\�E���A���������Ȃ��Q�Ɩ����{���ł��B�u�G�i�E�r�X�^��菟���Ă���Ɗm�M���܂��B |
||